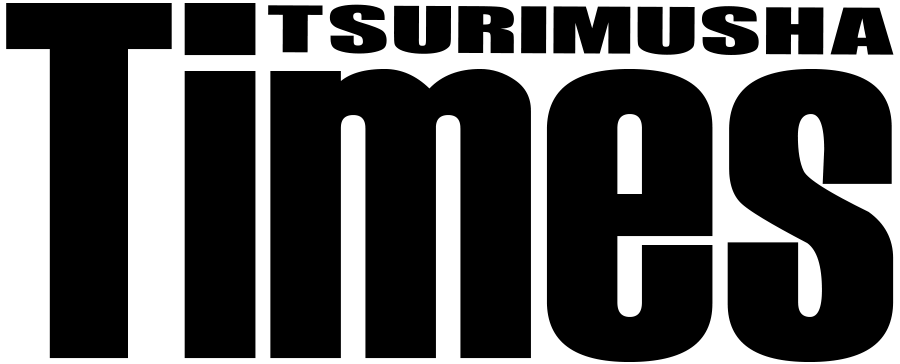

奥深き、紀州釣りの世界へ さぁ行ってみよう

釣りは世襲的な要素が強い趣味だといわれる。親が釣りをしていれば子供は小さなころから釣りに接する機会が多く、趣味になりやすいというもの。紀州釣りを理論立てて、この釣りの発展に尽力する永易啓裕さんもそうかと思いきや、実は違った。
「うちの親はまったく釣りをしないんですよ。僕が初めて釣りをしたのは小学2年の夏やったと思います。高槻(大阪府)の摂津峡に家族で川遊びにいったんですが、そのときたまたま親がセットの釣り道具を買ってきてくれてたんですよ。竹竿に玉ウキとか棒ウキが付いたようなものですね。それで釣るのが楽しくて、1日ずっと釣りをしていたら、もうあまりに一所懸命釣るもんだから、親が帰りに釣り道具屋を探してくれて一式揃えてくれたんですね。それをきっかけに釣りを始めました」
父方の実家が淀川に近く、祖父母の家に遊びにいっては祖父にワンドへ連れていってもらい釣りに打ち込んだ。
小学高学年になると行動範囲は広がり、兵庫県小野市の野池や奈良県生駒山上の湖へブラックバスを釣りに行ったり、大阪府の岸和田一文字へカレイ釣りに行き始める。交通手段はもちろん電車だ。
「ブラックバスはルアーなんですけど、釣れないときはミミズを付けたり淀川のワンドで捕っておいたモエビを使ったり、なんでもいいから釣りたかったですね」
ストイックに紀州釣りを極めるいまの姿からは想像できない貪欲さで魚を追いかけた。

インタビュー序盤からアツい話は止まらない
チヌに目覚めたのは中学2年のとき。チヌの魚体がかっこよく思えて無性に釣りたくなり、堺の沖堤防へ通い始める。
「ベテランそうなおっちゃんが大きいチヌを持って上がってくるのがうらやましくて、半夜釣りとか通し釣りで狙ってましたね」
1965年生まれの永易さんが中学2年生になる1970年代後半、警戒心の強いチヌを昼間の堤防で釣るのは難しく、夜釣りで狙うのが一般的だった。
「電気ウキでやったり、イチヨセをエサにコスリ釣り(堤防際をこするように探っていく脈釣り)で狙ったりしましたよ」
小さなチヌが通算で2、3尾しか釣れなかったが、チヌへの憧れは増すばかり。そんな永易さんに転機が訪れたのは高校1年の秋だった。
「釣り好きの同級生が泉南に引っ越したんですよ。それで、彼がよくいくエサ屋にいったとき『尾崎の漁港でチヌがぎょうさん釣れてるぞ』って聞いたんですね。『昼間にこうして釣る』って、紀州釣りのことですね。それでダンゴをひとそろえやってもうて尾崎の漁港へいったんです」
初めての紀州釣りに永易さんは夢中になった。
「アケミ貝のムキ身をエサに15cmくらいのチヌがけっこう釣れたんですよ。いま考えたら、たまたまタナが合っていなくて、ハワセ釣りみたいになってたんですね。そのときにね、強烈なアタリがあってアワせたらすごい引きで。周りのおっちゃんらは『ボラや。ボラや』っていうんですけど、上がってきたら36.5cmのチヌやって。そんな大きいチヌを釣るんは初めてやったから手が震えて、そのあとエサも付けられなくて。2、3投やって帰りましたもん」
この1尾で紀州釣りにどハマりしたのかと思いきや、そうではなかった。
「高校時代って釣りよりもっと楽しい遊びがたくさんあるんですよ。高校2年になると釣りそっちのけで街遊びでした」
18歳で運転免許を取り車に乗り始めると行動範囲が広くなって街遊びが減り出した。そして20歳を過ぎたころに釣りを再開。落とし込みやかかり釣りもやったそうだが、いちばん釣れたのは紀州釣りだった。
「僕はね、同級生や友達といってもぜんぜん釣れないほうやったんです。センスではよう釣らんというか。でもね、紀州釣りだけは頭で考えて、考えたことをやれば釣れた。どういうことかというと、いまサシエがどうなっているのか、ウキがこの動きをしたときはサシエが飛び出しているとか、こういうウキの感じやとサシエはダンゴから離れてないとか、そういう自分が思ったことが実際にできれば釣れるみたいなね。紀州釣りだけはちょっと違った。考えてやれば釣れる釣りなんやって思いました」

ヒレピンの綺麗な1尾にしてやったり。考えてやれば答えがでるのが楽しかった。
当時通っていたのが泉南の小島漁港にある小島養魚場だった。いまはマキエ釣りができないために紀州釣りは不可だが、当時は外側で紀州釣りが楽しめた。
「そのころの日曜日ってどこの釣り場も混雑してたんですよ。ただ、養魚場は有料で1日釣りをすると高かったので人が少なかった。高いけど週に一度の楽しみやからええかって毎週日曜日は通いました。そこで紀州釣りの基礎を身につけたんですが、22歳のときに、紀州釣りをもっとメジャーにしたいという気持ちが湧いてきたんですよ。
この釣りってチヌ釣りのジャンルのなかでもあんまり認められてないというか、釣具屋さんやエサ屋さんでチヌを釣るのにどうしたらいいかと聞いても紀州釣りは出てこないことが多いし、紀州釣り発祥の和歌山ですら『紀州釣りでも釣れるわ』っていわれるぐらいやった。それが腹立たしくてね。この釣りを誰かがメジャーにしてくれるのを待っていてもそんなことはないやろうから、自分が影響力を持つしかないって考えたんですね」

紀州釣りをもっとメジャーにしたい一心で永易さんはダンゴを投げ続ける
ちょうどそのころ、和歌山県衣奈でボーズをくらった帰り道に、湯浅のなぎ丸渡船の前を通り衝撃を受けた。
「店の前にチヌがまんたん置いてあったんですよ。なんであんなにチヌが釣れてるねんってくらい。なぎ丸には名前の知られた名人さんが通っていたのはあとで知ったんですけどね」
それをきっかけに永易さんの湯浅通いが始まる。
「初めていったときに上がったのは穴口やったんですけど、ポイントが分からない。4、5人が上がってたので、皆が並んだいちばん端に入ったんですよ。それでも5尾ぐらい釣れた。3回目か4回目にいったときに三のハエに上がる人がいなくて上げてもらったんですよ。36尾釣って、次にいったときも三のハエで19尾。2回目のときは陸に上がると船頭さんが会員カードを持って待ってましたわ。入ってくれるやろって。
このときにね、なぎ丸では年間ダービーをやっているのを知ったんかな。数(大漁)の部と大物の部があったんだけど、名前の知られている名人さんが何人もいたのでね、ここで目立つ釣果を出していれば何かきっかけがあるんじゃないかと思って年間ダービーの数の部を狙いにいったんです」
 クーラーに腰を下ろしてアタリを待つスタイルは今も昔も変わらない。なぎ丸のダービー優勝を狙って休みのたびに通っていた |
 湯浅の磯で竿を曲げる永易さん。頭で考えたことを実践できれば答えが出る。それを積み重ねて理論を構築していった |
その年にいきなり2位になったのもすごいが、翌年からはなんと4年連続優勝。小島で培った紀州釣りの基礎を湯浅の磯で進化、発展させた結果だが、大きな要因のひとつが永易ウキだった。

波乗りがよくて感度も抜群。永易さんの理想を具現化した永易ウキ
「小島時代はバルサを削った棒ウキを使ってたんですね。視認性がいいようトップの先にポチを付けてはいましたが、肩のフロートとかはない普通の棒ウキです。でもね、湯浅にそのウキを持っていってもぜんぜん役に立たなかったんです。湯浅は海底の高さにばらつきがあって、トントン(ウキ下=水深の状態)になるセッティングが毎投変わる。堤防に比べて波があるので棒ウキは波の上下で沈んだり倒れたりするので、寝ウキや玉ウキのほうが使いやすかった。でもね、寝ウキや玉ウキではアタリが出ない渋いときが続いたんです。どうしたものかと悩んでいるときに、常連さんがフロートを付けた棒ウキを使っていて『一回これを使ってみ』ってもらったんですね。視認性がいいようにトップの先端にポチを付けて使ったら、それまで分からなかったアタリが取れるようになりました」
棒ウキにフロートが付くことによって波で沈んだり倒れたりしなかったのだ。ただそれで満足はしなかった。より高感度で使いやすいウキの探求が始まった。
「浮力を抑えた形状で波に負けずに波に乗る形はどれなのか。フロートの部分も最初は台形でしたが、いろいろと試した末にそろばん形状にいきつきました」

そろばん型のフロートとトップ先端のポチが印象的な永易ウキ。水深や潮の速さに合わせてサイズをチョイスする
完成した永易ウキと圧倒的な釣果によって、雑誌などのメディアにも取り上げられる機会も増え、永易さんの名は全国に広まっていく。しかし、それだけでは満足しなかった。

自宅に飾られた数々の優勝カップやトロフィー
「4年連続優勝したころ、なんか自分の釣りが守りに入って攻めの気持ちがなくなっていることに気づいたんです。このままでは進歩がなくなるなって」
タイトル狙いをやめた永易さんは湯浅以外の釣り場にも積極的に足を運ぶようになる。愛媛県御荘湾や長崎県の五島列島、対馬、新潟県や山形県などへの遠征にも力を入れて経験値を増やしていく。
「ちょうど、ネットが普及しだしたタイミングだったので、ネットで知り合った人たちがいろんな形でバックアップしてくれました。ホームページが流行っていて、その中の掲示板でやり取りする形です」
既存メディアとインターネットにより、永易さんの名と理論はさらに広まっていく。SNSの時代に入ると永易さん自身も積極的に情報を発信し、近年は実際に釣りをしながら、視聴者とやり取りをするライブ配信を行うなど、紀州釣りのメジャー化への取り組みは精力的だ。

ダンゴの割れは紀州釣りの命。割れのコントロールが釣果を大きく左右する

誰でも再現できるのが永易さんの理論。それについてはまたの機会に
「紀州釣りは人生です。この釣りをしていなかったら、いまごろ何をしているか想像もできない。でも、こんなアツい気持ちで生きてはないでしょうね」
そんな永易さんが若い釣り人に伝えたいことを最後に付け加えておこう。
「せっかく釣りにいったのなら、惰性の釣りをするのではなく集中して釣ってください。そうでないと状況の変化に対応するセンサーが鈍っていきます。気づいているけどまあええかっていうのが続くと、まあええかさえも感じなくなる。集中できないときは休憩して、釣りを再開したら集中する。それを心がけてくださいね」