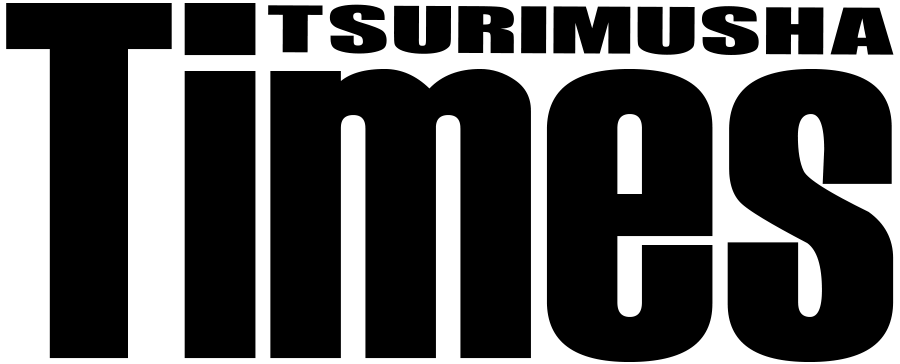
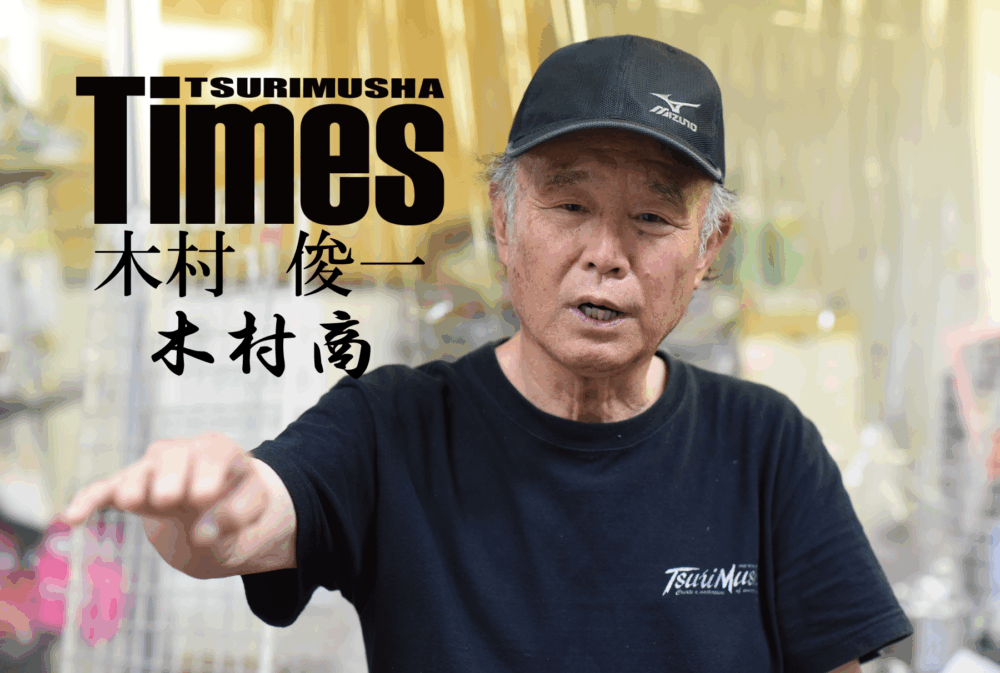
イシダイに魅了された木村商代表 木村俊一さんに迫る
「母方のおばあさん家がこの辺り(兵庫県尼崎市)の庄屋でね、おじいさん家は宮崎の貧乏なお寺やったんですよ。おじいさんは長男やったけど、弟が跡を継いで入り婿になった。そこの娘がお袋。親父のほうもこの辺の長屋に住んどった。日本鍛工の社員でね、そこのブラスバンドに入ってたんやけど、宝塚家劇団の楽団員募集を見て、それにうまいこと通って会社を辞めた。そのあとは歌劇団でテナーサックスを吹いてました」
そんな両親のもと、1952年3月に木村家の長男として俊一さんは生まれた。記憶に残っている最初の釣りは、小学校に入ったぐらいに、母方のおじいさんに連れていってもらった武庫川(兵庫県)河口のハゼ釣り。消し込まれるセルウキに竿を立てるとブルブルとくる手応えが面白かった。
「子供のころの遊びは釣りしかなかったからね。夏になると10cmくらいのカレイが河口から南部橋(武庫川最下流の橋)まで上がってくるんやけど、それがよく釣れましたわ。あのころの武庫川にはアユが遡上してて、4月は小アユ釣り。釣った小アユを天ぷらにしたのがご飯のおかずやったね」
そしてもうひとつ、楽団員の父親が気持ちを落ち着かせるために通っていたヘラ釣りについていくのも楽しみだった。
中学校に入ると友人たちと電車に乗って須磨や明石へせっせと通い、2年のときには「神戸愛釣会」に入会する。全日本サーフに所属するこのクラブでは、大人の会員に連れられて日本海や淡路島などにも出かけるようになり釣果にも恵まれた。
全日本サーフとは、1965年に創立された日本最大の投げ釣り愛好者団体の「全日本サーフキャスティング連盟」のこと。投げ釣りの技術の向上と、会員相互の親睦を深めることを目的とし、釣りの大会だけでなく、どれだけ遠くへ飛ばせるかを競うキャスティング競技も盛んだった。大物を釣った人や、キャスティング競技の上位入賞者にはバッジが贈られ、それらを帽子に付けるのが会員のステータスだった。
「大物賞のバッジもぎょうさん持ってるし、キャスティングにも凝ったから全国でベスト10とかのバッジもある。当時は富士工業とかオリムピックとかNFTとかメーカーのキャスティング大会も盛んやったからね。新幹線に乗って静岡までキャスティングの大会に行ったこともあるよ」
こうして木村さんは、釣りの深みにのめり込んでいく。

全日本サーフで投げ釣りに燃えていたころに獲得した大物賞やキャスティング競技での入賞をたたえるバッジの一部
「イシダイ釣りを始めたのは18歳のころ。当時イシダイいうたら花形やから釣りたくてね。初めてのイシダイ釣りは日ノ岬(和歌山県)へ親父といってんけど、両軸リールとか使ったことないやんか。パーマ(バックラッシュ)とか、すかたんばかりで釣りにならんかった」
大学では釣りクラブに入会。イシダイに憧れる木村さんを知った学釣連(全日本学生釣魚連盟)のメンバーが、イシダイ釣りに詳しい釣具店を紹介してくれた。ここのご主人は、後に入会することになるイシダイ釣りの精鋭軍団「日本釣魚研究会」の事務局長だった。
「店に行ったらな、竹竿が用意してあんねん。竹竿やないとイシダイは釣れへんって。これを買わないんやったらイシダイ釣りはやめとき、中途半端にやっても釣れへんからっていわれて。リールもね、アブの9000番がええよって」
大卒の初任給が5万円ほどのころ、1万6000円の竹竿と2万円のリールを購入した木村さんは、先輩と和歌山の釣り場へ通い始めるが、まったく釣れなかった。
「当時は釣り人も多くて、ポイントにも入れなかったからね。あまりにも釣れへんもんやから、釣具店のご主人が屋久島(鹿児島県)やったら釣れるからってすすめてくれて。最初行ったときは、小さいハタが釣れただけやったけど、もう一回行って段取りしてもろうた2回目やったね」
屋久島南岸の尾之間地区、ヤビチという磯で、ピトンに掛けた竹竿が強烈に舞い込んだ。
「竿を起こしたことは覚えてるけど、あとはどないしたんかまったく覚えてへん。気づいたら魚が横たわってた。魚釣りであんなに興奮したことなかったからね、たまらんかった」
初めての石物は55cmのイシガキダイ。イシダイ釣りを始めて2年、1971年夏の出来事に木村さんはノックアウトされた。その後、半年も経たないうちに60cmクラスを数尾釣ったあと72cmのクチジロを仕留め、海に向けて竿が突き刺さる置き竿の釣りにどっぷりハマったのだった。
日本釣魚研究会にも入会し、イシダイ釣りにますますのめり込んでいくのだが、近場のイシダイ釣りは厳しかった。
「クラブでは毎月大会してたけど、150人が参加して釣れるんは3尾とか。27cmのイシガキでも釣ったらラッキーやなっていうてたもん。だって、竿がずらーっと並ぶねんから釣れへんよ。いまは1人で10尾のイシダイやけど、当時は10人で1尾やん。そやから、出し抜いて釣るっていうか、よう釣る人の仕掛けを学んで、状況に合わせて変化させたり、エサにしてもそうやん。食用の赤貝でよう釣る人おったけど、昔はそんなんで釣ってるっていわへんから。勝手に覚え、勝手に盗めって世界やったからね」
様々な仕掛けを駆使し、いまそのときに魚が欲しているエサは何かを考えて、柔軟に臨機応変に対応する木村さんのスタイルは、こうして築かれていった。
 24歳のころ日本釣魚研究会のメンバーによる屋久島遠征。右端が木村さん、左端が牧田会長 |
 25〜27歳のころにほぼ同期のメンバーと出かけた男女群島遠征の1枚。中央が木村さん |
大学卒業後はサラリーマンになったが、日曜日の釣りだけでは満足できなかった。
「日曜日は人でいっぱいで釣れへんの分かってるやん。狙いは月曜日。そやから会社をサボって行ったりしたけど、お袋に月曜日は会社に(休むと)電話しといていうたら、すごくいやがりよんねん(笑)。そやけどな、会社をサボって大きいイシダイ釣っても、店に遊びに行っても、釣具屋の主人はイヤな顔をするし、やっぱりサボっていくんはよくないなって。クラブの人らは自営業ばっかりでしょっちゅう釣りに行ってたから、あんなんええな、仕事としてやらないかんと思って釣具屋を始めたんですわ」
木村さん29歳のときだった。

釣具店を始めたころに遠征した男女群島での1枚。誰に気兼ねすることなくイシダイ釣りに行けるようになる
「最初はね、とにかく売らなあかんからジャンルを問わずに何でも置いたけど売れへん。うちに回ってくるメーカーの営業の人に『イシダイ専門にするか、安売り店のどっちかを選んだほうがいいですよ』っていわれて、それやったら大好きなイシダイ一本でいこうと。31歳のときですわ」
店に置くアイテムを少しずつ増やしていくなかで、竹竿が当たった。東京の竿師を訪ねて仕入れた竹竿を店に置くと、それを求めてお客が一気に増えた。当時、関西でイシダイの竹竿を扱う店は珍しく、木村さん自身が竹竿で釣りまくっていたことも大きかった。そしてもうひとつ、木村さんが作る仕掛けもヒットした。
「市販品にないものを作ってほしいって依頼があって作ってたんやけど、それなら最初から作ったものを店に並べようと。その後、縁があって釣武者さんがブランドで出してくれるようになって波に乗れた感じやね」
ちなみに屋号の「木村商」は、クラブの会長の奥さんに四柱推命で見てもらったもの。
「変な屋号で最初はいややってん。足らずというか尻切れトンボみたいやん。普通やったら木村商店とか木村商事とか木村釣具店やんか。でも四柱推命で見てもらうと「商」で止めるんがええんやって。お願いした手前逆らわれへんし。でもね、皆が「木村商、木村商」っていいだして、どこにでもある名前ちゃうから、いま考えたら木村商でよかったなって思いますわ。開店日時も昭和56年(1981年)5月16日の12時にしなさいっていわれてね。そんなんがあったから、店を始めたときのことはよく覚えてますわ」

42歳の春、柏島のムロバエ群礁、アンパンでの1枚
定休日は月曜日。日曜日の夜になるとお客さんが車で訪れ、閉店と同時に釣り場へ向かった。春の乗っ込み期は四国西南部や男女群島、それらが落ち着くと紀伊半島、夏から秋は島根県隠岐や徳島方面、そして冬場は屋久島へ出かけた。その後、行動範囲はさらに広がり、東京の青ヶ島や小笠原諸島など夢の島々への遠征もこなし、まさにイシダイ釣りの最前線を突っ走っていくのだった。
さて、置き竿をメインに手持ちの釣りや遠投釣りをこなし、大物から数釣りまでマルチにこなす木村さんの金字塔ともいえる1尾が1978年5月13日に男女群島の立神で仕留めたクチジロ84.5cmだ。当時の日本記録となったこの魚は、ハナグリ瀬戸のシンボルともいえる立神で仕留めたもの。
「その前に強烈なんがきたんやけど切られてね。次にまたきた。すごい締め込みに竿が立てなくて、一緒に上がった仲間に起こしてもうて。必死に巻いてたら白いのがぼわんと浮いてきた。それがでっかいクチジロや。うれしいというか怖かったな。帰ってきてから神社にお祓いにいったよ」

店に飾られているクチジロ84.5cmの剥製。当時の日本記録を塗り替えた1尾

2003年4月に男女群島の上の赤瀬・ビョウブで仕留めた71cm、7.3kg。男女群島では中尾瀬で71.5cmの本イシを仕留めている
男女群島への許可船が登場して2年目の快挙。木村さんはその後も男女群島へは毎年通い、本イシでは71.5cmのデカバンをはじめ数え切れないくらいの石物を仕留めている。また、魚影が濃い男女群島では、仕掛けやエサ、釣り方など様々なテストを繰り返して、イシダイの習性を学ぶとともに、釣技を発展させていった。
瀬ズレやハリスなど仕掛け類から始まったオリジナル商品は、2000年代に入ると竹竿の調子を再現した3本継ぎのカーボンロッドやチタンのピトンなどアイテムを増やし、石鯛キングブランドでリリース。SNSの時代が到来すると積極的に情報を発信しイシダイ師の心を大いにくすぐった。そんな木村さんが近年力を入れていることのひとつが、大物をカラー魚拓に残すこと。

近年はカラー魚拓にも力を入れる。タカノハダイやイガミ(ブダイ)のほかにもカンムリベラやモンガラハギなどレアな魚拓も
「昔、アオタ(アオブダイ)の10kg超えとかイガミ(ブダイ)の55cmとか釣ったことあるねんけど、魚拓にしてなくて、歳いってからしまったと思ってね。写真では物差しを置いて撮っても大きさが分からへん。魚拓のサイズは正味やから、真実味があるやん」
大物との一期一会を大切に石物はもちろんのこと、タカノハダイやカンムリベラ、モンガラハギなど魚種を問わずにカラー魚拓に残している。
その1枚1枚に秘められた物語をまたうかがいたいものだ。

木村商の天井には所狭しとデカバンの魚拓が貼られている。